COLUMN
コラムページ
2025/03/19
建設解体工事
解体工事の揺れの原因とは?周囲への影響や対策を紹介!

「解体工事が始まったら、家が揺れて不安…」「この振動で周囲の建物に影響が出るのでは?」そう思う方もいらっしゃるかもしれません。 解体工事では、様々な要因で揺れが発生します。結果、ヒビ割れや地盤沈下などの被害が起こる可能性もあり、施工の前に事前準備と対策を行うことが必要です。 本記事では、解体工事で発生する揺れの原因や影響、振動を抑えるための対策、さらには近隣住民とのトラブルを防ぐ方法を詳しく解説します。解体工事による揺れが気になる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
佐賀県を中心とした
建物解体、廃棄物処分なら
各種認定企業の坂井商店に
お任せください
TEL0952-98-0118
営業時間 9:00~20:00 定休日 無休
解体工事で発生する揺れとは?
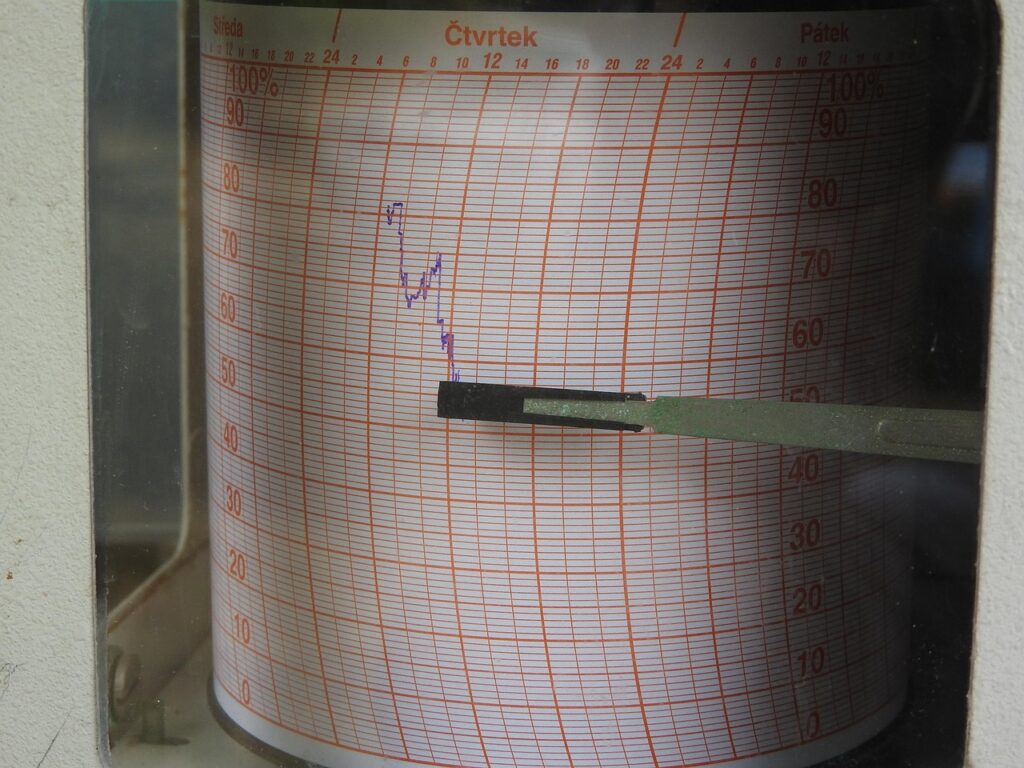
解体工事では、建物を取り壊す際にさまざまな要因で振動や揺れが発生します。これは、工事に使用する重機の動きや、建物の構造、さらには周囲の環境などが影響するためです。
特に、大型の建物や密集した住宅地での解体工事では、近隣への影響が大きくなることがあり、住民にとっては「自宅が揺れている」「建物にダメージが出るのでは?」などの不安を感じることも少なくありません。
なお、揺れの程度は工事の方法や規模によって異なりますが、事前の準備や適切な対策を行うことで、影響を最小限に抑えられます。
解体工事で近隣が揺れる原因
解体工事による揺れは、重機の振動・建物の構造・外部環境の影響が主な原因として挙げられます。事前の準備や対策を検討するために、それぞれの原因を詳しくご紹介します。
重機の使用による振動
解体工事ではさまざまな重機が使用されますが、その中でも特に振動の影響が大きいのが、コンクリートを砕くための油圧ブレーカーや、地面を掘削するバックホーなどです。
油圧ブレーカーはコンクリートの基礎部分や壁面を破壊するために、強い衝撃を連続的に与える仕組みを持っています。これにより発生するその振動が地面に伝わり、揺れとなって周囲に伝わってしまいます。
また、ブルドーザー・クレーン・クローラーダンブなどのキャタピラで移動するバックホーやクローラー式の重機は移動するだけでも地盤に圧力をかけるため、小さな振動が長時間にわたって続きます。さらに、大型の重機を使って建物を倒す際には、その衝撃が直接地面に伝わり、一瞬ではあるものの大きな揺れが発生することがあり、近隣の住民からのクレームにも繋がりかねません。
建物の構造による振動
解体される建物の構造によっても、発生する振動の大きさや伝わり方は異なります。頑丈で大きな建物の構造であればあるほど、解体が難しくなり、それと比例して振動が発生する可能性も大きくなるというイメージです。
例えば、鉄筋コンクリート造の建物は頑丈に作られているため、破砕の際に大きな衝撃を与えなければ解体ができません。大きな衝撃は重機などで物理的に発生させるため、振動もまた発生しやすくなります。また、鉄骨造の建物では、解体時に鉄骨が倒れることで大きな振動が生じることがあります。
木造建築の場合、コンクリート造や鉄骨造に比べると振動は抑えられます。しかし、築年数が古く、劣化が進んでいる建物では、解体時に想定外の崩れが起きることもあり、その衝撃が振動となって周囲に伝わるため、注意が必要です。
天候や周囲の環境による振動
解体工事による振動は、天候や周辺環境にも影響を受けます。最も大きな要因は、風雨による地盤状態の変化です。一般的に、軟弱な地盤では振動が伝わりやすく、地盤が硬い場所では振動が吸収されやすくなる傾向があります。
雨が降ると地盤が緩み、振動がさらに広がることが想定されます。また、風が強い日には、解体した建材が飛散し、それが地面に落下することで追加の衝撃が発生する危険性も見過ごせません。
さらに、解体工事が行われる場所の環境も大きく影響します。例えば、住宅が密集している地域では、振動が建物同士に伝わりやすく、影響が増幅されます。また、幹線道路沿いの現場では、大型車両の通行による揺れが加わることで、振動がより強調されることもあります。
解体工事実施の際は、周辺環境や実施時期も検討要素として関わってくることをおさえておきましょう。
解体工事で揺れる際の影響とは?

解体工事による揺れは、単なる振動として感じるだけでなく、周囲の住宅や生活環境にさまざまな影響を及ぼすことがあります。特に、建物の構造や地盤の状態によっては、目に見える形でダメージが発生する場合もあり、近隣住民にとっては大きな不安要素となります。
ここでは、住宅そのものへの影響と、日常生活への影響を詳しく見ていきます。
住宅への影響(ヒビ割れや地盤沈下)
解体工事で発生する振動は、周囲の建物にも影響を及ぼすことがあります。特に築年数の経った住宅や、もともと耐震性に不安のある建物では、外壁や基礎部分にヒビ割れが生じる可能性があります。小さなヒビであれば問題ないように思われるかもしれませんが、そこから雨水が浸入することで建物の劣化を早める原因となるため、甘く見てはいけません。
また、地盤が軟弱な地域では、振動が地盤の沈下を引き起こすこともあります。これにより、家がわずかに傾いたり、地面に亀裂が入ったりすることがあり、最悪の場合、建物の基礎部分にまで影響が及ぶことも。特に、地下室や半地下構造の住宅では、地盤の変化が影響しやすいため、注意が必要です。
生活への影響(騒音やストレス)
解体工事による影響は、建物への物理的な被害だけではありません。日常生活にもさまざまな形で影響を与えます。その代表的なものが、騒音によるストレスです。
解体作業では、コンクリートを砕く音や重機が動く音、建材が落下する音などが発生します。特に油圧ブレーカーなどの重機は、振動とともに大きな音を出すため、近隣の住民にとっては長時間の騒音被害となります。昼間の作業が主ですが、在宅で仕事をする人や、小さな子ども、高齢者がいる家庭にとっては、日常生活に支障をきたすほどの影響を受けることもあります。
また、解体工事による振動や騒音が続くことで、心理的なストレスを感じる人も少なくありません。「家が揺れている気がする」「壁にヒビが入るのではないか」などの不安が、精神的な負担となることもあります。特に、工事期間が長くなると、こうしたストレスが積み重なり、近隣住民とのトラブルに発展するケースに注意が必要です。
このように、解体工事による揺れは、住宅そのものに影響を及ぼすだけでなく、住んでいる人々の生活にも大きな影響を与える可能性があります。
解体工事の振動に関する法律と基準
解体工事による振動は、近隣住民の生活環境に大きな影響を与えるため、一定の法律や基準によって規制されています。特に「振動規制法」は、工事現場で発生する振動を適切に管理するために制定された法律であり、各自治体によって運用されています。
トラブルを未然に防ぐためにも、振動の測定基準や、違反した場合の罰則の概要を把握しておきましょう。
振動規制法とは?
振動規制法は、工事や工場の稼働によって発生する振動を抑える目的で制定された法律です。この法律では、振動の発生源となる施設や作業に対して一定の基準を設け、住環境への影響を最小限にするよう求めています。解体工事では特に、重機の使用やコンクリートの破砕による振動が問題視されるため、事業者側が適切な対策を行わなくてはなりません。
具体的には、振動が一定の基準値を超えないように管理することが求められています。基準値は自治体ごとに異なり、地域の状況に応じて定められるため、工事を行う前には該当する地域の条例を確認しましょう。
佐賀県では、「振動規制法に基づく振動の規制地域及び規制基準」として、地域別に基準値を設定しています。
違反した場合の罰則と対応策
振動規制法に違反した場合、事業者には行政指導や罰則が科されることがあります。特に、基準値を超えた状態で工事を継続した場合や、事前の届出を怠った場合は、自治体から改善命令が出され、罰金や工事停止などの措置が取られるケースも想定されます。
また、近隣住民が振動による被害を訴えた場合、適切な対応を怠ると民事訴訟に発展する可能性を想定しなければなりません。解体工事の施工者・依頼者として、トラブルを避けるためには、事前に振動測定を行い、問題が生じる前に対策を取ることが大切です。
住民への説明を丁寧に行い、不安を取り除く努力をすることも、スムーズな工事進行につながります。
解体工事の揺れを軽減するための対策

解体工事に伴う振動は、周囲の建物や住民の生活に影響を及ぼすため、できるだけ抑える工夫が求められます。特に、振動の原因となる重機の選定や、適切な施工方法を採用することが大切です。
実際の解体工事現場の状況や、解体工事業者の規模によって、採用できる対策は変わるため、状況に応じた対応を選択できるようにしておきましょう。
低振動型の重機を使用する
解体工事では、重機の使用が避けられません。しかし、近年は振動を抑えた低振動型の機械が登場し、環境への影響を軽減できるようになりました。
例えば、油圧ショベルのアタッチメントとして、衝撃を分散させるブレーカーやクラッシャーを導入すれば、周囲の地盤や建物への負担を抑えられます。また、リモート操作による解体ロボットも選択肢の一つです。これらの機器を活用すれば、従来よりも安全性を高めながら振動を減らせるでしょう。
防振シートや防音パネルを設置する
防振シートや防音パネルの設置は、振動を低減するうえで効果的な手段の一つです。例えば、防振シートは振動エネルギーを吸収し、周囲への影響を抑える働きを持っています。
加えて、防音パネルと併用すれば、騒音と振動の両面に対処可能です。これにより、近隣住民への負担が軽減され、工事に対する理解を得やすくなります。これらの設備は、比較的設置が容易なため、多くの現場で採用される対策です。
工法を工夫する
解体工事では、施工方法の工夫によって振動を抑えられます。例えば、一度に大規模な解体を行うのではなく、建物を部分的に取り壊していく方法を採用すれば、振動の発生を最小限にとどめられるでしょう。
また、「湿式工法」では、作業中に水をまくことで粉じんの発生を抑えつつ、振動の広がりも軽減できます。あるいは、「切断工法」を使えば、建物を大型のカッターで細かく切断しながら解体するため、周囲への影響を最小限に抑えることも可能です。
近隣住民とのトラブルを防ぐ方法
解体工事では、振動や騒音が原因で近隣住民とのトラブルが発生することがあります。ここからは、円滑に工事を進めるために気を付けるポイントをいくつかご紹介します。
工事前に近隣住民へ説明を行う
解体工事に伴う振動や騒音に対し、住民が不安を抱くのは当然です。工事が始まる前に説明会を開いたり、個別に案内を配布したりすることで、住民の認知と理解を得ておきましょう。
説明では、解体工事業者にも同席してもらい、工事のスケジュールや発生する振動・騒音の程度、対策を明確に伝えることが大切です。また、住民からの質問や要望に丁寧に対応すれば、信頼関係の構築につながるでしょう。こうした配慮を怠ると、後々のトラブルにつながる恐れもあるため注意が必要です。
事前に建物の状態を確認・記録する
解体工事による振動が周囲の建物に影響を及ぼす可能性があるため、工事前の現状を把握しておくことが必要です。具体的には、近隣の建物にひび割れや地盤沈下の兆候がないかを調査し、写真や動画で記録を残しておきましょう。
また、記録を残す際には、単に外観を撮影するだけでなく、建物の基礎部分や壁の内部の状況も可能な限りチェックすることが大切です。後々トラブルが発生した際、証拠として活用できるよう、撮影日や調査担当者の情報も併せて記録しておくことを忘れずに。
さらに、確認作業の結果は、近隣住民にも共有しておくことが望ましいです。「工事前の状態」として事前に認識を合わせておくことで、工事後に「新たなひびが入った」「地盤が沈下した」などの苦情が出た際に、冷静に対応できます。
振動測定を行い、安全基準内で作業する
解体工事に伴う振動が近隣の建物や住民に与える影響を最小限に抑えるためには、事前の振動測定が欠かせません。特に、振動規制法の基準を超える揺れが発生すると、建物の損傷や住民の健康被害につながる可能性があるため、計画的な測定が求められます。
振動測定は、専用の計測機器を用いて工事現場周辺の振動レベルを数値化し、安全基準内で作業が行われているかをチェックするものです。測定は通常、工事前・工事中・工事後の各段階で実施され、振動が規定の範囲内に収まっているかを確認します。もし基準値を超える振動が発生した場合は、作業方法の見直しや重機の使用制限を行い、影響を抑えるための対策を検討しなければなりません。
また、振動測定の結果は記録として残し、近隣住民へ共有することで、工事の透明性を確保できます。住民の中には「工事の影響で家が揺れているのでは?」と不安を抱える人もいるため、測定データを示すことで、根拠に基づいた説明が可能となります。このような対応を行うことで、住民との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐことにつながるでしょう。
まとめ|揺れの原因や対策を理解し、解体業者に相談しよう
解体工事による揺れは、重機の使用や建物の構造、周囲の環境などが影響し、住宅のヒビ割れや生活環境の悪化を引き起こす可能性があります。しかし、適切な防振対策、振動測定を行うことで影響を軽減できます。
これらの対策に加え、近隣住民への事前説明や建物の状態記録を行うことで、トラブルを防ぐことも大切です。工事を安全かつ円滑に進めるためにも、信頼できる解体業者に相談することから解体工事の検討を始めましょう。坂井商店では、解体工事における不安に対しても真摯に向き合い、対策をしっかりと行っております。お気軽に(https://381sakai.com/contact/ )までお問い合わせください。
佐賀県を中心とした
建物解体、廃棄物処分なら
各種認定企業の坂井商店に
お任せください
TEL0952-98-0118
営業時間 9:00~20:00 定休日 無休


